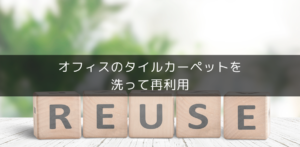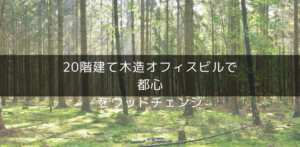今回は、ちょっと違った観点で、価値観を刺激出来たらと思います^^
<カップヌードルの蓋を留めるシール>
1年くらい前の話ですが、カップヌードルの蓋を留めるシールが無くなりました。

蓋と素材の違うプラシールを使うのではなく、同一素材の紙に爪を2つ作ってそれを折り曲げると蓋が止まるというモノです。
日清食品さんが出した当時のプレスリリースがこちらです。
これを見た時にいくつか思いました。
積極的に生活者(消費者)に活動を訴求する事で自社のサステナビリティブランドが高まる事
積極的に生活者(消費者)に活動を訴求する事で生活者の意識を変革する事ができる事
⇒ さらにはそれが日常的に無意識な状態でサステナビリティな活動が当たり前にやっている事
特に後者の「生活者」への影響はとても大きいなと思います。
日清食品さんの年間の販売数量は分からなかったのですが、カップヌードル全体だと年間38億食近く日本人は食べているそうです。
スゴイ量ですよね。
この数量が誰かしらの手元に渡りに目に触れ、体験するわけなので、メディアとしてのパワーはとんでもないなと思います。
<ファミマのエコ割シール>
同じようにこれもちょうど1年前くらいの事です。
もう一枚の写真も私が実際に撮った写真です。

ファミマ以外は、今でも「割引シール」だったり「値下げシール」だったり、とにかく「安い=お得」を訴求しています。
一方で、ファミマはそこはあえてエコ割としています。
もともと消費期限が近付いた食べ物は廃棄されていたので、「エコ割」という表現がバッチリだと思いますが、
それ以上に、生活者(消費者)へのインパクトも大きいなと思っています。
今までは「安くてお得だから買おう」となっていたのが「捨てられるのを救済する為に買おう」という人が少なからず増えていると思います。
そして、ファミマのエコ割で感化された人は、他のスーパーの割引シールを見ても「お得文脈」で買うのではなく「救済文脈」で買う人が増えているのではないかと思います。(あくまで私の推測ですが、おそらくそういう影響は多分にあると思います)
つまり、このファミマのエコ割のシールもまさしく「サステナビリティ認知のメディア」となっていると思います。
そう考えると、やはり企業の役割(特にB2C企業)は、とても大きいなと思います。
顧客接点となる商品そのものが、何かを伝えるメディアになるので、それをどう伝えるかがホント大事だなと思います。
単純に機能的価値を提供するのではなく、どんなメッセージ性を持って提供するかで、同じ商品も価値の大きさが変わってきますね^^
投稿者プロフィール

- 外資系大手コンサルティングファームにて経営・IT・業務に関するコンサルティングを行い、生命保険会社にて経営企画部長を従事、Fintechベンチャー起業・経営を経て、「サステナビリティを1歩でも前進させたい」というパーパスを具現化すべくCircular Economy Thinking合同会社を起業。これまで培った経営コンサルティング経験、起業経験・経営経験を活かし、Circular Economy実践の為の活動を行っている。他にもCXコンサルティングやエグゼクティブコーチングも行う。
最新の投稿
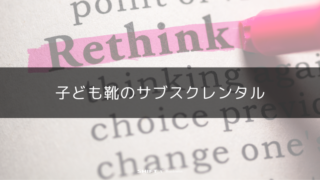 02:Rethink(R1)2025年1月18日[v2.0] 子ども靴のサブスクレンタル
02:Rethink(R1)2025年1月18日[v2.0] 子ども靴のサブスクレンタル 09:Repurpose(R7)2025年1月13日修理するという体験価値の提供
09:Repurpose(R7)2025年1月13日修理するという体験価値の提供 11:Recycle(R8)2025年1月6日未来を見据えた太陽光パネルのリサイクルイノベーション
11:Recycle(R8)2025年1月6日未来を見据えた太陽光パネルのリサイクルイノベーション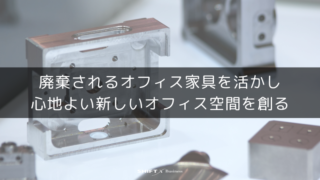 08:Remanufacture(R6)2024年12月27日廃棄されるオフィス家具を活かし、心地よい新しいオフィス空間を創る
08:Remanufacture(R6)2024年12月27日廃棄されるオフィス家具を活かし、心地よい新しいオフィス空間を創る